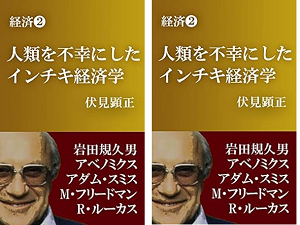書籍化しました

続きです。
《サンフランシスコ講和会議以降は日本と「大人の関係」となったオーストラリア》
昭和30年代から「高度経済成長期」に突入した日本経済。
高度経済成長とは・・・・Wikiより

飛躍的に経済規模が継続して拡大することである。好景気時の実質経済成長率が約10%以上を表す。
毎年、実質(物価上昇分を除く)経済の成長が10%超なんて、デフレが普通になった今の日本では、到底想像もつきませんね。
ただ、私の記憶に鮮明なのは、父の月給が、毎年春に上がり続けたこと。
「春闘」とか、労使交渉での「ベースアップ」とも言います。
当然ながら、母も機嫌が良かったです。
注目すべきは、公務員(教員も含む)の月給も、「人事院勧告」で「民間並み」といって、タイムラグがあっても、同様に順調に上がり続けました。
★高度成長の時は、商品も売れれば、設備投資も絶好調です。
自動車を作るのも、船舶を作るのも、住宅を作るのも、橋や列車を作るのも、全てに「鉄」が不可欠です。
そこで、不可欠となるのがオーストラリアの豊富で良質な鉄鉱石と石炭です。
私が記憶にあるのは、その時代の新聞記事で、毎年、日本の大規模鉄鋼メーカーの、当時の新日鉄、日本鋼管、川崎製鉄、住友金属、神戸製鋼らが、オーストラリアの「鉱山主」との年間の購入計画と、価格交渉です。
いつも、日本側に押し切られていました。
「去年よりも、多めに買うから、値引きしろや」という感じでしたね。
鉄鉱石はともかく、石炭は日本でも取れました。
麻生太郎さんの筑豊炭田や、北海道など。
しかし、硫黄分が多いので、鉄鋼の精製には品質が悪かったのです。
それで、鉄鉱石も、石炭もいきおい、オーストラリア一辺倒となりました。
この状況は、中国が高度成長期に入り、鉄鋼の生産が日本を追い抜く21世紀まで続きます。
★「資源輸出」に特化するオーストラリアは、戦後はある意味「日本の経済圏」に組み込まれたともいえるでしょう。
その意味では、オーストラリアにとって宗主国イギリスは「縁遠くなった親戚」状態でしょう。
スポンサードリンク
《オーストラリアの首相は何故、選挙の度に「親日派」と「親中派」が交代するのか?》
親米で、西側自由主義国としては、安全保障も含めて日本と価値観を共有します。
しかし、高度経済成長を終えた中国は鉄鋼の生産量は、日本を抜いて世界一です。
当然、鉄鉱石と製鉄用の石炭(コークス)のお客様としては、中国様様なのです。
背に腹は代えられないといったところでしょうか?
★気持ちはわかりますが、3年ほど前にあった、世界一の日本の海上自衛隊の潜水艦の技術のオーストラリアへの技術供与の話、ご破算になってよかったです(笑)
中国に、漏らされたら、日本の「海の防衛」は終わりでしたから。あ~怖い。
★前代のターンブル首相の息子さんの嫁さんは中国共産党員ですからね。
マルコム・ターンブル前豪首相とは・・・Wikiより

政策・主張
所属するオーストラリア自由党は保守系の政党であるが、ターンブル自身はリベラル派であるとされており、本人も2015年の党首選挙後の会見の中で「本当の意味でのリベラルな政府を目指す」と述べている。
オーストラリアにおける共和制導入を支持しており、 アボット前首相が復活させた「ナイト」と「デイム」の称号についても時代遅れであるとして授与の廃止を発表した。
ターンブルは中国について「オーストラリアと抗日で戦った最も長い同盟国だ」と述べ、最大の貿易相手国である中国を最重視する親中派と見られている[日米豪印の枠組みを継続させ、中国がオーストラリア国内で権益買収の動きを見せた際は反対するなど、あくまで豪州の国益を棄損しない限り中国の台頭を歓迎する「現実主義的」親中の立場であると一部から評価されることもある。ただし、中国によるダーウィン港の99年租借を認めたことは駐留拠点が近い米国から苦言を呈されることもあった。
2015年12月18日に来日。首相就任後の東アジアで最初の訪問国に日本を選んだ。安倍晋三首相との会談では、日本の捕鯨に対して深い失望を伝える一方、日本の平和安全法制の支持、自衛隊とオーストラリア軍の共同訓練の推進を表明し、中国に対しては南シナ海での埋め立ての停止を求めることで一致し、東シナ海での動きに強い反対を示した。
2017年1月28日、2016年アメリカ合衆国大統領選挙により誕生したトランプ大統領と電話会談を行い、オバマ政権との間で結んだ難民の受け入れに関する合意を履行するように迫った[15]。
家族・親族
息子は、中国政府のアドバイザーとして活躍していた中国共産党党員の娘と結婚している。
長々と、回り道しましたが、結論は、チャーチルが述べた、言わば「超然主義」
「イギリスはEECなんかに加盟しなくともやっていけるんだ」という「旧英連邦自力更生主義」は失敗したということです。

オーストラリアも、ニュージーランドもカナダも、戦後早々と日米を中心とした「環太平洋経済圏」で生きていくことにきめて、現在に至っています。
イギリスは女王に敬意を表すといえども、距離も時代も遠い「ご先祖様」でしょう。
《ド・ゴールが死んでやっとECに入れてもらったイギリス》

1967年の2度目の加盟申請もド・ゴールの反対で却下されました。
そして、目の上のたん瘤のド・ゴールが1970年に死にます。
やっと1972年1月にECに加盟できました。
★イギリスがECに加盟したのは、アメリカからドイツを監視するために命令されたのだという「説」がネット上に転がっていました。
面白い説ではありますが、現状、検証できていないので、紹介するにとどめます。
続きます。